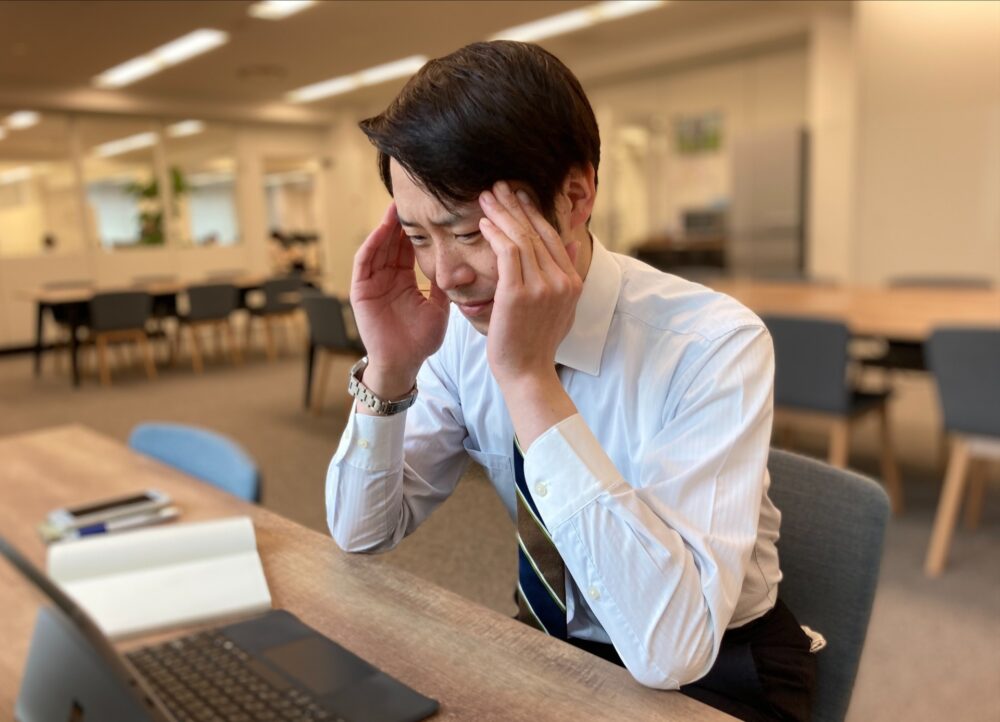医療ミスによって心身に深い傷を負ったとき、多くの方が悩むのが「慰謝料はどれくらい請求できるのか」「どう進めればよいのか」といった問題です。
突然の医療過誤に直面して、何が正しい対応なのか判断できず、不安なまま時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。
実際には、慰謝料の金額や請求の方法はケースによって大きく異なり、適切な手順を踏まないと本来得られるはずの賠償を受け損なうこともあります。
本記事では、慰謝料相場や請求手続き、被害の証明方法、さらには裁判例までを詳しく解説しています。
正しい知識を得ることで、冷静かつ納得のいく対応ができるようになります。
最終更新日: 2025/6/23
Table of Contents
医療ミスによる慰謝料の相場
過去の裁判例に見る慰謝料金額の目安
死亡慰謝料は一家の支柱で約2,800万円、後遺障害慰謝料は等級に応じて110万円~2,800万円が目安です。
入通院慰謝料は、通院・入院期間や程度により異なりますが、例えば6か月入院で244万円、6か月入院後6か月通院で282万円などが裁判例の目安です。
裁判例では和解金や判決額がこれら相場に沿うケースが多く、状況によっては大きく増減します。
慰謝料に含まれる要素と内訳
慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の三要素に分かれ、それぞれ精神的・身体的苦痛に対して支払われます。
なお、治療費・休業損害・逸失利益などは、慰謝料とは別に損害賠償金の構成要素として請求されます。
精神的・身体的被害に関する慰謝料の算出方法
算定方法は、交通事故の裁判基準が参考にされ、通院・入院の期間や後遺障害等級、死亡時の家族構成などから総額が算定されます。精神的苦痛の程度や法律上の認定基準が重視されます。
医療ミスの種類によって異なる慰謝料の傾向
手術ミスや誤診、説明義務違反など医療ミスの種類により、後遺障害の程度や被害者の状態が異なるため、慰謝料額にも差が出ます。
重大なミスほど高額になりやすく、具体的な事例に応じた慰謝料の算定が必要です。

医療ミスで慰謝料請求する前にやるべきこと
主治医・病院への説明要求と証拠の確保
医療ミスへの対応は、まず主治医や病院に対して正式に説明を求めます。
状況に応じて、会話の録音や診療録や検査結果等のカルテ開示請求を行い、証拠を確保することが重要です。
特に改ざん防止には、弁護士を通じた証拠保全手続きが効果的とされます。
また、通院日数など慰謝料算定に必要な記録も整理しつつ記録を収集しましょう。
損害賠償請求の要件(債務不履行・不法行為の立証ポイント)
損害賠償請求には、①医師や病院の過失(債務不履行または不法行為)、②その過失による損害発生、③損害と過失との因果関係、の医療過誤の3要件が必要です。
診療ミスと悪化した症状との因果関係を証明して、診療記録・検査結果等を証拠としてそろえる必要があります。
なお、債務不履行および不法行為の双方を適切に組み立てた主張が求められます。
<参考>
医療過誤の3要件とは?損害賠償請求の流れも解説|医療訴訟・医師意見書

医療ミスによる慰謝料請求の方法
弁護士に依頼
医療ミスで慰謝料や損害賠償を求める際は、まず医療紛争に詳しい弁護士に相談・依頼すべきです。
専門家による診療記録の分析、因果関係や過失の立証支援、手続き戦略の策定などを通して、適正な賠償を確保する体制が整います。
また、証拠保全手続きや訴訟・示談交渉などを一貫して任せられる点も大きなメリットです。
医療鑑定
慰謝料請求において、医療鑑定は診療行為や被害の因果関係を評価する重要手段です。
通常、弁護士が収集した各種資料と分析結果を、協力医が専門的な立場で医療過誤の3要件に該当するかを調査します。
鑑定結果は証拠として裁判や示談交渉で活用され、特に過失や後遺障害の程度を客観的に証明する役割を担います。
弁護士が、依頼先の協力医選定や、医師意見書の作成依頼を行うのが一般的です。
<参考>
示談交渉
示談交渉は、裁判に至らず和解を目指す手段です。弁護士が代理人として医療機関と交渉します。
弁護士は、協力医による医師意見書や損害額の根拠となる証拠を提示したうえで、慰謝料や休業損害、逸失利益など総合的な賠償を取りまとめます。
<参考>
医療訴訟の医師意見書|160名の各科専門医による圧倒的実績
調停と医療ADR
裁判外で紛争解決を図る調停や医療ADRは、第三者(通常は弁護士複数名や医師)が間に立つ仕組みです。
日弁連の制度では、過失責任の有無にとらわれず話し合いを通じて妥当な解決案を探ります。
訴訟より短期間で、かつ当事者双方に納得感のある合意を形成しやすい手続きです。
医療訴訟
示談交渉や医療ADRで合意に至らない場合、裁判を経て正式に医療機関を訴えることも選択肢となります。
訴訟では、診療契約に基づく注意義務違反(過失)やその結果としての損害、因果関係の三要件を立証する必要があります。
証拠となるカルテや鑑定書など収集と分析が重要なので、弁護士の専門的な訴訟能力が不可欠です。

慰謝料請求におけるポイントと注意点
裁判例から見る慰謝料請求成功のポイント
裁判では、診断ミスや説明義務違反などが争点となった事例が多いです。
勝訴のポイントとして、①医師の注意義務違反、②患者の被害と因果関係、③後遺障害の程度の立証が挙げられます。
特に「高度の蓋然性」に基づく証明が重要視される傾向です。協力医による医師意見書や検査記録が裁判所の判断に大きく影響しています。
医療訴訟は長期戦
医療訴訟は手続きが複雑で、審理・尋問・証拠調査に時間を要し、数年単位で長期化する例も珍しくありません。
協力医による医療調査や意見書の準備、証拠収集の労力も必要です。そのため、心理的・経済的負担を考慮して、余力があるか慎重に判断する必要があります。
示談や和解での解決も検討する
訴訟の長期化リスクや負担を軽減するため、示談や裁判外紛争解決手続(医療ADR)、調停などを検討することが推奨されます。
示談交渉や医療ADRによる和解の方が、当事者双方の精神的負担が少なく、早期解決が図れる事例が多いです。
メディカルコンサルティングができること
医療ミスなのかについての医療調査
医療訴訟の多くは、単に治療結果が悪いだけで医療ミスではありません。単に治療結果が悪いだけでは、医療訴訟で勝てる確率は著しく低いです。
勝訴できる可能性の無い不毛な医療訴訟を防ぐためには、第三者による、医療ミスかどうかについての医療調査の実施が望ましいです。
弊社では、ほぼすべての科の事案で医療ミスか否かの医療調査(意見書作成可否調査)が可能です。詳細は、以下のコラム記事をご確認ください。
<参考>
医療事故における医療調査の基本内容とは?費用も解説|医師意見書
医療調査できる診療科一覧
弊社では、以下のようにほぼ全科の医療調査を実施できます。
- 整形外科
- 脳神経外科
- 耳鼻咽喉科
- 眼科
- 消化器外科
- 呼吸器外科
- 心臓血管外科
- 産婦人科
- 泌尿器科
- 脳神経内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 呼吸器内科
- 腎臓内科
- 血液内科
- 小児科
- 放射線科
- 精神科
- 皮膚科
- 形成外科
- ⻭科
- 麻酔科
- 救急科
- 感染症科
- ペイン科
- 病理
医療訴訟で使用する医師意見書
意見書作成可否調査で医療ミスであることが判明した場合、各科の専門医による顕名の医師意見書を作成することが可能です。
医療ミスの可能性がある事案で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
尚、個人の方は、必ず弁護士を通じてご相談ください。個人の方からの直接のお問い合わせは、固くお断りしております。
<参考>
医療訴訟の医師意見書|160名の各科専門医による圧倒的実績
医師意見書の作成にかかる費用
医療調査(意見書作成可否調査)
医療訴訟用の医師意見書を作成できるのかを判断するために、医療調査(意見書作成可否調査)を必須とさせていただいています。
意見書作成可否調査では、各科の専門医が、診療録や画像検査などの膨大な資料を精査いたします。
概要 | 価格 |
基本料 | 140,000円 |
動画の長い事案 | 170,000円 |
追加質問 | 45,000円 / 回 |
※ すべて税抜き価格
※ 意見書作成には医療調査(意見書作成可否調査)が必須です
※ 意見書作成には別途で意見書作成費用がかかります
※ 意見書作成に至らなくても医療調査の返金は致しません
医師意見書
医療調査(意見書作成可否調査)の結果、医療ミスが判明して、医師意見書を作成する際には、別途で医師意見書作成費用がかかります。
概要 | 価格 |
一般の科 | 400,000円~ |
精神科 | 450,000円~ |
心臓血管外科 | 500,000円~ |
施設(老健、グループホームなど) | 350,000円~ |
弊社が医療訴訟で医師意見書を作成した実例
弊社には全国の法律事務所から医療訴訟の相談が寄せられます。これまで下記のような科の医師意見書を作成してきました。
- 脳神経外科
- 脳神経内科(神経内科)
- 整形外科
- 一般内科
- 消化器外科
- 消化器内科
- 呼吸器外科
- 心臓血管外科(成人)
- 心臓血管外科(小児)
- 循環器内科
- 産科
- 婦人科
- 泌尿器科
- 精神科
- 歯科
一方、眼科や美容整形外科の相談は多いものの、医療過誤と認められるケースは少なく、弊社においても医師意見書の作成実績は限られています。

医療ミスの慰謝料でよくある質問
示談金と慰謝料の違い
示談金とは当事者間で合意した解決金、慰謝料は精神的苦痛を補填する賠償金の一部です。
示談では慰謝料を含む損害賠償全体をまとめて「示談金」と称することが多く、実質的に同等の意味を持ちます。
示談の合意文書は契約的性格が強く、一度成立すると後から変更できません。
示談の際は慰謝料と他の損害項目が漏れなく含まれているか確認が必要です。
慰謝料請求が認められるケース・認められないケースは?
慰謝料請求が認められるには「医療ミスによる負傷や後遺障害など心身の損害」が必要です。
不法行為や債務不履行に基づいて、過失の存在・因果関係・損害の具体性が証明されれば認定されます。
一方、治療結果が思わしくなかっただけでは医療ミスと認められず「ただのリスク」と見なされ、慰謝料は支払われないケースが多いです。
医療ミスの治療費は医療機関に請求できる?
治療費は「積極損害」として完全に賠償請求でき、示談や裁判で支払対象となります。交通費、付添費、将来の介護費用なども同様です。
治療費の請求は医療記録や領収書など客観的証拠に基づく必要があり、証拠不備だと争点になります。
示談交渉で提示された治療費のリストに漏れがないか、しっかり確認することが重要です。
医療ミスで慰謝料をもらった場合税金はかかりますか?
原則として、医療ミスによる慰謝料や治療費、損害賠償金は非課税(所得税・住民税とも)です。
国税庁によると、「心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など」は非課税とされています。
ただし、事業所得などとみなされる部分や、社会通念上不当に高額な見舞金等は課税対象となる場合があります。
なお、故人が受け取る前に死亡した場合、その賠償請求権は相続財産となり、相続税の課税対象となるため、税理士に相談することが推奨されます。
まとめ
医療ミスによる慰謝料は、被害の内容や重さによって大きく異なります。
死亡事故では2,800万円、後遺障害では110万〜2,800万円、入院・通院の期間によっては数百万円に及ぶこともあります。
慰謝料は精神的・身体的苦痛への賠償であり、治療費や休業損害などとは別に請求されます。
請求には医療ミスの立証や因果関係の証明が不可欠で、弁護士や医療鑑定の協力が重要です。
裁判は長期化しやすく、示談や医療ADRも有効な選択肢です。
医療ミスの慰謝料で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
尚、個人の方は、必ず弁護士を通じてご相談ください。個人の方からの直接のお問い合わせは、固くお断りしております。
関連ページ
- 医療裁判で勝てない理由と勝訴する方法|医療訴訟の医師意見書と医療鑑定
- 医療過誤の3要件とは?損害賠償請求の流れも解説|医療訴訟・医師意見書
- 病院を訴える前に知っておくべき医療訴訟の注意点|医療調査・医師意見書
- 癌の見落としで損害賠償請求できる条件は?|医療訴訟・医師意見書
- 胸部レントゲンの肺がん見落としは損害賠償請求できる?|医療訴訟・意見書
- 健康診断の見落としは損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書
- 手術ミスは損害賠償請求できる?裁判の注意点は?|医療調査・医師意見書
- 癌の誤診でよくある事例は?損害賠償請求も解説|医療訴訟・医師意見書
- 癌の病理検査が誤診かどうかの確認法は?|医療訴訟・医師意見書
- 胃腸炎と盲腸の誤診で損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書
- 膵臓癌の誤診は損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書
- 大腸癌の誤診で病院に損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書
- MRIの誤診で損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書
- 精神科で起こりやすい事故は? 訴訟事例も解説|医療訴訟・医師意見書
- 美容外科で失敗されても訴訟が難しい理由は?|医療調査・医師意見書
- 採血時に神経損傷しやすい部位は2ヵ所|医療訴訟の医師意見書
資料・サンプルを無料ダウンロード
以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。